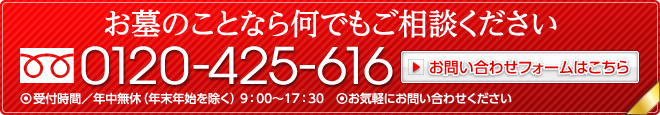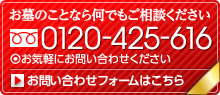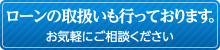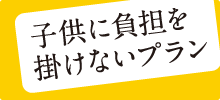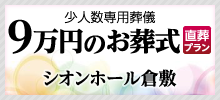お答えしますQ&A
Q&A
「永代使用料」って何ですか?
「墓の守り手がいる限り、期限を定めずに使用できる権利」という意味です。
ですから、墓地を買うといってもあくまで(墓地は)借地であって、墓地所有権は、借地権のようなものです。 また、墓地の使用者が毎年霊園に納める管理料は、霊園内通路の管理やゴミの焼却・水道料などに使われる費用です。 各自の墓地内の掃除や草とりなどの管理は、基本的に含まれていません。
墓地の広さは、どのくらいが適当でしょうか?
4㎡、6㎡、9㎡の区画が人気です。
お客様が建立されるお墓にもよりますが、人気のある区画サイズは「4㎡」「6㎡」「9㎡」です。
例えば、
4㎡の場合、間口・奥行きともに2m。
6㎡の場合、間口2メートル・奥行き3m。
9㎡の場合、間口・奥行きともに3m。
また、○聖地と表記されている場合は、1聖地=90cm×90cmとお考えください。
寿陵(じゅりょう)とは、どんなお墓でしょうか?
生前に、あらかじめ建てておくお墓のことを、寿陵といいます。
昭和64年1月に昭和天皇がお亡くなりになり、2月24日の大喪の令(天皇のご葬儀)の後、その日の夕方には『武蔵野陵』(東京・八王子市)で葬儀が行われました。これは、ご生前に御陵(みささぎ)が造られていたから可能だったのです。
現在、正確な統計はありませんが、やすらぎ石材ではお客様の内、およそ2〜3割ぐらいの方がお元気なうちにお建てです。
そして、その割合は徐々に増えてきております。
寿陵をご希望される方は、
●子や孫に、経済的に負担をかけたくない。
●自分たちの入るお墓を建てて、見ておきたい。
●自分たちの希望する形にしたい。
●子どもたちが遠方にすんでいるため、世話をかけたくない。
●子どもたちが頼りにならない…
など、様々な理由がおありのようです。
お墓のお掃除の仕方を教えてください。
掃除の仕方
お掃除に使用する洗剤は、一般的な中性洗剤をご使用ください。
●樹木が多く汚れやすい場合
汚れに水分を含ませた後、市販の金属製品のヘラでこそげ取ってください。キレイに簡単に落ちます。(ヘラはホームセンターで購入できます)
●目地の汚れ・文字の汚れ
毛の柔らかいブラシや雑巾で掃除してください。
●最後に水で流し、きれいな雑巾で拭きます。
お供えの仕方
●腐りやすいものは、その日に持ち帰る
腐ったものの置きっ放しは、仏様がいやがります。
また、鳥が来たりするなど、お墓も汚れます。
お酒などをお墓にかける方がいらっしゃいますが、お酒に含まれる糖分が付着して汚くなります。ビンや紙パックのままで、お供えしましょう。
●鉄分はダメ!
ジュース・缶詰など鉄製のものは、お墓に置き去りにするとサビが出てお墓に付着し汚くなります。サビが付着した場合、石材店にサビ落としの薬剤がありますので、早めにご連絡ください。
お墓の建てる方角に、決まりはありますか?
一般的に、お墓の向きは東から南に向けて、建立することが多いです。
ただし、厳密な決まりがあるわけではないので、やすらぎ石材では特に狭い墓所の場合など、「お墓の向き」よりも「お墓参りのしやすさ」等を考慮して建立した方がよいと考えております。
お墓は、いつまでに建てればいいでしょうか?
三回忌(命日より2年目)までに、約80%の方が建てられます。
その内70%の方が、一周忌までに建てられます。
「早く建てた方が良い」「七回忌までに建てれば良い」などは、昔の土葬だったころの名残りで言われているだけで、具体的な根拠はありません。
最近では四十九日までに建てる方も増えています。
いつ建立しても、残された家族が元気で気持ちよくお参りできることが、一番の供養ではないでしょうか。
お墓に、お骨(骨壷)は何個入りますか?
先祖墓「10寸三重台墓」で9個ぐらい、
夫婦墓・個人墓「8寸二重台墓」で2個ぐらい、お骨が入ります。
地域・葬儀社などで違いがありますが、骨壷(カメ)の直径は18cmぐらいが一般的です。
お骨を骨壷から出して、サラシの袋に入れ替えて納骨すると沢山入ります。
先祖墓のスタイルはできてまだ日が浅いのですが、夫婦単位で納骨すると20個入るとして、300年ぐらいでいっぱいになります。
外国産の石の品質が気になるのですが。
国産の石と比べても大差ありません。
インド・中国・ポルトガル等の石は、既に長年の実績があり、同じ地球の花崗岩(庵治石も大島石も花崗岩)ですから、そんなに大差はありません。
また、普段見かけるビルの壁や床、今温泉とともに人気の大浴場などにも使われていますが、とても綺麗です。
もちろん『墓石』としても使われ、最近需要の多い洋型やオリジナル型には良く合い、お客様のご希望を叶える石がたくさんあります。
安い石はやわらかく、水を吸う石は良くないのでしょうか?
どちらも、正しいとは言えません。
例えば、岡山県笠岡の北木石(きたぎいし)は、比較的安い石ですが、硬く、墓石や鳥居、日本銀行の外壁にも使われています。
また、水を吸わない石は有りません。確かに、水を吸いやすい石と吸いにくい石があり、吸いにくい方が風化が遅いので良い石と言うことが出来るということです。
分骨は良くないのでしょうか?
遺骨を分けて、良くないことが起こるという心配はありません。
歴史的に『分骨』は、お釈迦様の死を悲しんだ8人の仏弟子たちが、その徳をしのんで遺骨を分けて祀ったのが始まりと言われています。そして、仏教の言い伝えによれば、分骨したところに"ストゥーパ(舎利)"が建てられ、それを中心にして寺院が形成されたと言うことです。
一方現代、実際には、火葬場で收骨の時、お骨の全てを拾うことは、まずありません。骨壷には、五体のごく一部しか納まらないのが普通なのですから、遺骨を分けてよくない事が起こるという心配は無用なのです。
「うるう年」にお墓をさわってはいけないって本当?
特に差し障りはございません。
広島や九州方面で『うるう年』を気にされる方が、多いと聞きます。
そもそも江戸時代、4年に一度、倹約を推し進める制度があったそうで、そのなごりからきたようです。
岡山県やその他の県では『うるう年』に関係なくお墓が建っていますが、特に差し障りはないですね。
霊園・墓地を買いたい(売りたい)のですが。
やすらぎ石材では霊園・墓地の分譲、買い取りもしています。
新しくお墓を建てたい方はもちろん、引っ越しに伴うお墓移転のための霊園・墓地の分譲、買い取りの事も、やすらぎ石材にお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。